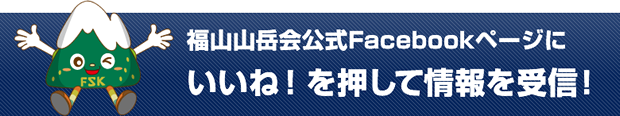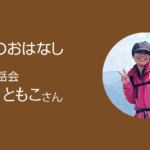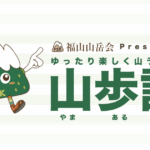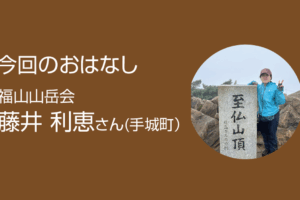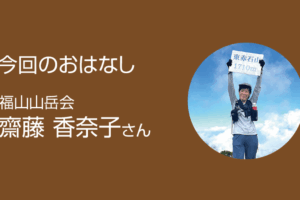皆さんは日本一の巨木と聞いて何を思い浮かべますか?縄文杉?屋久杉?実はどちらでもなく、日本一の巨木は鹿児島県姶良市にある「蒲生の大クス」というクスノキなのです。その大きさは、高さ・根回りともに30mを超すほどで樹齢も1500年と、まさに神様のような大樹です。今回、5月の屋久島山行の前日に寄り道して見に行ったのですが、そのあまりの大きさにメンバー全員が唖然とし、そのあと笑ってしまいました。次の日の屋久島でも、ついついこの木と比べてしまい、屋久杉が小さく見えてしまったほどです(笑)。
そもそもクスノキはどういう木なのでしょうか?クスノキはクスノキ科の常緑樹で、西日本沿岸部に多く分布しています。葉や樹皮には薬を思わせる芳香があり、この特有の香りから古代人は不思議な木だと感じたのか「霊妙な」という意味の古語である“くすし”木ということで、クスノキという名が付いたとされています。また材は柔らかく、加工がしやすいわりに耐久性が高く、仏像や船、神社仏閣の建材として使われており、厳島神社の大鳥居は現在でもクスノキが使われているそうです。文学や歴史の観点から見ても、クスノキは古事記・日本書紀をはじめとして風土記、枕草子、太平記にも登場しており、まさに日本文化にはなくてはならない存在といえるでしょう。
かつて古代の日本人は、自然物に神様が宿ると信じていました。山で巨樹に出会うと、現代の私たちでも不思議と自然への畏敬の念を抱かずにはいられなくなります。そんな感情が、山や自然を大切にする気持ちの原点なのだろうと思います。そういった気持ちを忘れないようにしたいものです。
クスノキについて
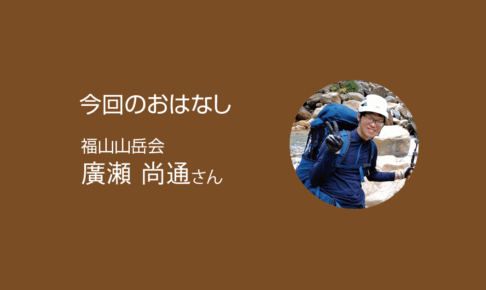
この記事が気に入ったら
いいねしよう!
最新記事をお届けします。