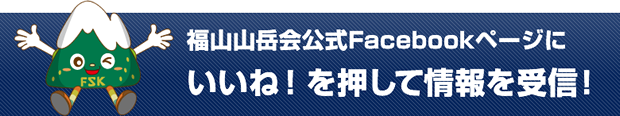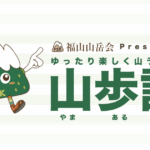山での遭難事故の原因には、道迷い・滑落・悪天候・持病・低体温症などがあります。今年のGW中の遭難者数は207名、そのうち死者は23名でした。2018年の登山者人口は約530万人と推測されていますが、連休中だけでもこれほどの遭難者が出ているのは多い気がします。事故を防ぐための方法はなかったのでしょうか?ちょっとした装備の不備や未熟な登山知識が遭難事故につながります。私たちは連休中に北アルプスの新穂高から涸沢岳西尾根を登り、滝谷を偵察し涸沢岳・奥穂高岳に登頂しました。予定を変更し時間があったため、穂高岳山荘前で2時間ほど休憩しました。涸沢から奥穂高岳に登るルートは人気のルートですが、奥穂高岳に登るには積雪があるので上級者レベルの経験と技術が必要です。しかし今回は初心者に近い人もおり、雪山装備が不十分な人、道具を使いこなせていない人、悪天候時に低体温症になりそうな服装の人、グループでロープを繋いで中級者・初心者ばかりでアンザイレンしている人など見かけ、遭難されなければよいがと心配しながら上高地に下山しました。
悪天候の時は二重遭難防止のため救助活動は行なわれません。天候が回復するまでの間は、自分自身で命を守らなければなりません。そのためには、予備の食糧やしっかりとした装備などが必要です。連休のたび毎回のように遭難事故のニュースを目にしている気がします。事故の無いことを願い、福山山岳会では経験豊富な人たちが各種講習会を行っています。そのことが一般の登山者の方々にも伝わっていくことで、少しでも事故を減らすことができればよいと考えています。