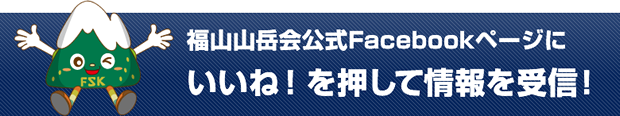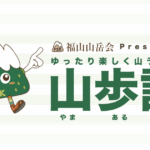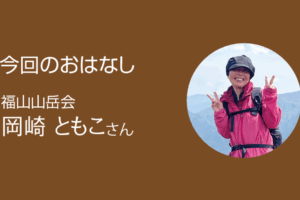ぐらんふぁーまの読者には「深田久弥」という人の名を聞かれた方も多いと思う。1964年に新潮社から発刊されたこの小説家の手に成る随筆集「日本百名山」は発刊から50数年経った時、この山岳随筆が昨今の登山ブームのきっかけになったことは疑う余地がない。筆者自身も日頃あちこちの山に登る際、その登る山がこの本に書かれた山かどうか話題にすることがある。
しかしながら日頃接するベテランクライマーの口からあまりこの「日本百名山」へのこだわり、いわんや「登山ブーム」という言葉が聞こえてこないのはなぜだろうか。おそらく彼らが山に登るという行為は、もっと違った次元のところにあるのかもしれない。山に登ること、スポーツではなくその「文化」には包容力がある。可憐な高山植物へのいたわり、霊山への畏敬の念、山人とのふれあい、難壁への挑戦、ランプの下での自分自身の省察、過酷な氷雪との会話、筆者自身年齢を重ねるごとに薄れていく「何事でもやってみようという気持ち」の呼び起こし、それらどんな欲求も山は素直に受け入れてくれる。もちろんその果実を得るには山に登る者と、自然そしてその山との相性次第であるが。筆者が勝手に選んだ「福山十名山」、熊ヶ峰、蔵王山、彦山、大弥山、蛇円山、馬乗山、大谷山・・・。それらどの山の頂に立っても、福山の町並み、あるいは瀬戸の穏やかな内海が臨める、なんと素晴らしいふるさとの情景であろうか。山は登るすべての者とその哀楽を分かち合ってくれると思っている。