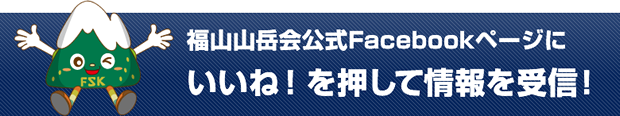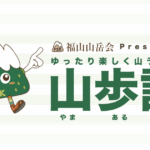みなさんの近所には、どんな山がありますか?なんの変哲もない山も、名前の裏にある歴史を紐解けば、見る目が変わるかもしれません。今回は、そんな山の名前の由来の話をしましょう。
一般的に、山の名前は大きく6つのタイプに分類できます。① 山の姿形や色など様相を名付けた山、② 生き物や住んでいた人・城や家など、山にいたもの・あったものの名前を付けた山、③ その山から見えるものを名付けた山、④ 山にまつった神仏の名前を付けた山、⑤ 主要な山や町から見て、どの方向にあるのかを名付けた山、⑥ それ以外の特殊な名前の山(富士山など)それでは、実際になじみの山を見てみましょう。
さて最初は、福山の人にとっては「親の顔ほど見た」蔵王山。蔵王山は、蔵王権現という仏様を山頂にまつったことからその名がつきました。現在、本尊は山の東側にある医王寺に移されています。平安時代、奈良の吉野山の僧侶が蔵王権現を全国各地に布教したことがあったそうです。山形県にある蔵王山も、同じ時代に名付けられたそうですよ。
次に紹介するのは竜王山。広島や岡山には「竜王山」という山が多くありますが、これにも深い理由があります。瀬戸内海沿岸は、雨が少ない地域が多く、農作業をする人たちにとって水不足は死活問題でした。そこで、水の神である竜神に雨乞いをするため、山の頂上に竜の王様である「タカオカミ」という神様をまつったことに由来するそうです。
山の名前には、歴史・気候風土などさまざまな情報が隠されています。
山に登れないこれからの雨の時期、山の名前の由来などを調べてみてはいかがでしょうか。