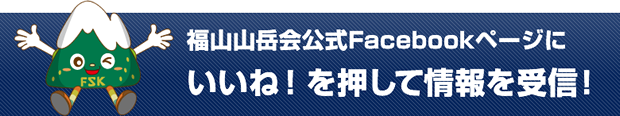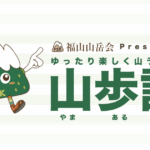日本で一番広い村は?と聞かれた時、何となく北海道とか東北をイメージする人は多いと思うが、国内で一番広い村は奈良県吉野郡十津川村である。
私が「十津川村」を意識し始めたのは40数年前だった。漢詩に関連した一つの語句の疑問符を模索して、辿りついたモノの本の中に、孝明天皇をして「今夜は十津川郷の者が門を守っているから、安心して眠ることができる」と言わしめ、更に幕末の京都、近江屋で坂本竜馬が暗殺された時、竜馬の警戒網を瞬時に破ったのは刺客の一言「十津川郷の者です」だった。「十津川村」とはどんな村か?「十津川郷士」とは?「十津川村へ行ってみたい」
ちなみに十津川郷士は武術に優れ、神武天皇を八咫烏(やたがらす)として、熊野から大和橿原まで先導(道案内)したとか、幕末には尊皇攘夷を唱え京都御所を守衛していたとされる。
頭の隅の漠然とした想いが叶ったのは、今から約20年前、「熊野古道・小辺路(こへち)」を二泊三日で歩いたことだった。これを機に熊野古道の何本ものルートを歩いたが、原点はやはり十津川村だった。
我々一行は、幕末動乱の舞台の一つでもあった五條市を過ぎ、野迫川村の叔母子岳(1,344m)直下の叔母子峠から念願の十津川村に入った。この広大な村には標高1,000m以上の山が100座以上存在する。(広島県内には20座)その昔「鳥も通わぬ十津川の里」と言われ、また、大和国と紀伊国の国境(奈良・和歌山県境)は、今も果無峠(はてなしとうげ)と呼ばれている。何時の時代、誰がこんなにもロマン溢れる名を付けたのだろうか。